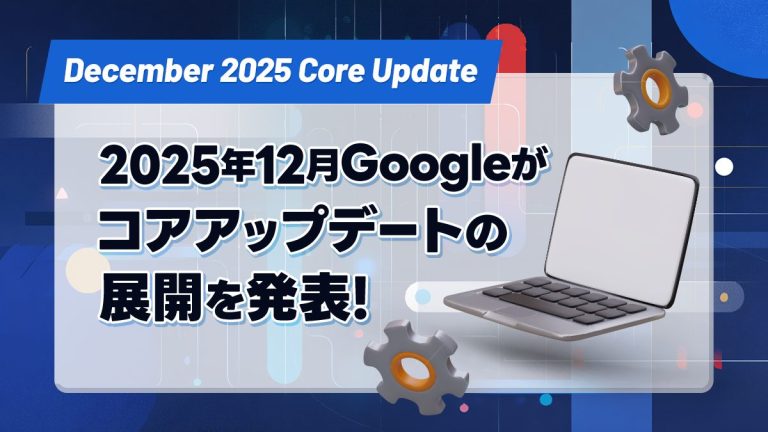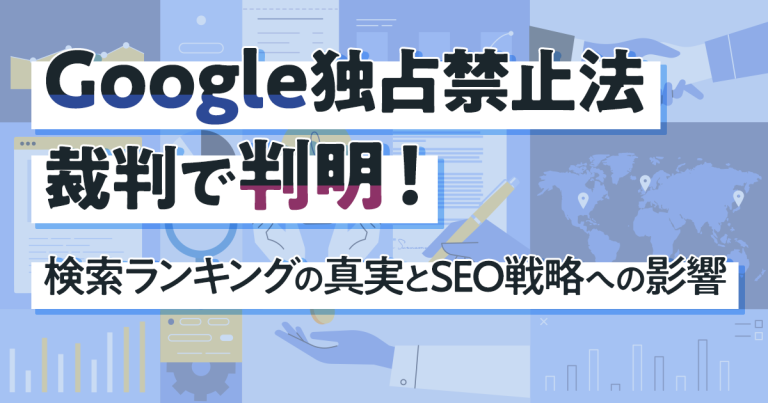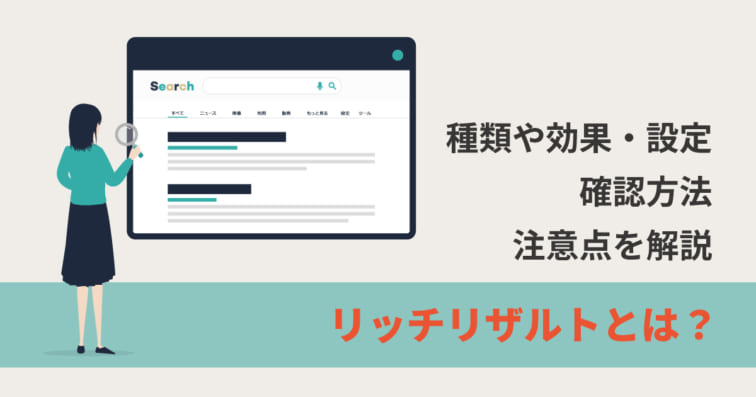クエリファンアウトとは?WebサイトのAI検索流入を伸ばす「お悩み解決コンテンツ」の作り方

最近、Google検索にAIによる回答が表示されるようになり、「自社サイトのアクセスが減るのでは…?」と不安を抱くWebサイト担当者の方も多いでしょう。
しかし、AIがどのようにして回答を生成しているのか、その仕組みを理解すれば、この変化はむしろ大きなチャンスになります。
その核心にある技術が「クエリファンアウト」です。これは、ユーザーが入力した一つのキーワードの裏にある「本当に知りたいであろう様々な質問」をAIが予測・分解し、それらの質問に答える情報をWeb上から探し出して要約する仕組みを指します。
つまり、AIが予測する複数の質問に1ページでまとめて答えることができれば、AIに引用されやすくなり、結果としてトラフィックを増やす大きなチャンスになるのです。
この記事では、明日からあなたのWebサイトで実践できる「AIに引用されるお悩み解決コンテンツ」の作り方を徹底的に解説します。
なぜ今、Web担当者が「クエリファンアウト」を知るべきなのか?
結論から言うと、Google検索に「AI自動案内係」が登場し、ユーザーがあなたのサイトにたどり着く前の行動が大きく変わるからです。
これまでユーザーは疑問を持つたびに何度もキーワードを変えて検索を繰り返していました。しかし、AI Overviews(AIによる概要)の登場により、検索結果ページだけで多くの疑問が解決できるようになりつつあります。
AI Overviewsの登場はユーザーの行動を大きく変える可能性があり、結果としてWebサイトへの直接の流入が減少する懸念も指摘されています。
このAI Overviewsという回答は、その裏側にある「クエリファンアウト」という根幹技術によって生成されています。
クエリファンアウトを一言で説明すれば、GoogleのAIがユーザーの検索キーワードから「本当に知りたいであろう質問群」を予測し、それらの質問に答える情報をWeb上から集めてきて要約して提示する仕組みです。
つまり、あなたのWebサイトがこの「AI自動案内係」の情報源として選ばれなければ、ユーザーに存在すら知ってもらえない、という事態が起こり得るのです。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
- 「クエリファンアウト対策」を全く新しい作業と捉えず、これまで行ってきた「顧客理解を深めるためのSEO活動」の延長線上にあるものと考えてください。なぜなら、「『クエリファンアウト』って、結局SEOと何が違うんですか?」という質問を本当によく受けるからです。答えは「目的は同じ、でもアプローチが少し変わる」です。これまでのSEOが「キーワード」を軸にしていたのに対し、これからは「質問の集合体」に答える視点が重要になります。この本質を理解することが、最初の大きな一歩です。
AIに「引用される」コンテンツの秘密は「サブクエリ」の網羅
では、どうすればAIに「情報源」として選ばれるのでしょうか。その鍵は、クエリファンアウトが分解する「サブクエリ」を理解することにあります。サブクエリこそ、ユーザーの曖昧な検索意図を具体的な疑問に分解したものなのです。
例えば、あるユーザーが「乾燥肌 化粧水」と検索したとします(これはECサイトの例ですが、BtoBのSaaSツールであれ、地域の専門サービスであれ、考え方は全く同じです)。
AIはこの検索の裏に、以下のような複数の「サブクエリ=隠れた疑問」が存在すると推測します。
- そもそも乾燥肌の原因って何?
- どんな保湿成分が効果的なの?
- 敏感肌でも使える製品はある?
- 価格帯はどれくらい?
- 敏感肌でも使える製品はある?
- 実際に使った人の口コミや評価は?
- 正しい使い方は?
そしてAIは、これらのサブクエリそれぞれに最も的確に答えているWebページを探し出し、情報を統合してAI Overviewsを生成するのです。
この仕組みを理解すると、私たちが作るべきコンテンツの姿が見えてきます。
それは、一つのキーワードに応えるだけでなく、そこから派生するであろうユーザーのあらゆる疑問(サブクエリ)に先回りして、一つのページで包括的に解決する「お悩み解決コンテンツ」です。
AIに選ばれる「お悩み解決コンテンツ」3つのステップ
クエリファンアウトの仕組みを理解した上で、具体的に明日から何をすればいいのでしょうか。ここでは、私がお客様に必ずお伝えしている3つのステップをご紹介します。
ステップ1: ユーザーの「隠れた質問」を洗い出す
まずは、ユーザーがあなたのサービスや情報にたどり着くまでに抱えるであろう、あらゆる疑問を徹底的に洗い出します。キーワードツールを眺めるだけでは不十分です。
例えば、以下のようなリサーチを行うとよいでしょう。
- Yahoo!知恵袋を深掘りする
- どんな保湿成分が効果的なの?
- 営業担当やカスタマーサポートにヒアリングする
- SNSやレビューサイトを分析する
リアルな悩みの宝庫です。「サービス名 〇〇」などで検索し、どんな質問が投稿されているかリストアップしましょう。
人間が検索するキーワードに対し、Webページを上位表示させるための施策
顧客から日々寄せられる質問の中に、最大のヒントが隠されています。
良い評価だけでなく、ネガティブな意見にこそ「期待と現実のギャップ=ユーザーの疑問」が表れています。
ステップ2: 質問に答えるパーツを「構造化」する
次に、洗い出した質問への回答を、AIが理解しやすい「パーツ」として整理します。文章で長々と説明するのではなく、情報を整理して提示する意識が重要です。
- 機能や料金プランの比較
- 導入手順や利用方法
- サービスの特長やメリット
「table」タグを使った比較表で整理します。
「ol」タグを使った番号付きリストで解説します。
「ul」タグを使った箇条書きで簡潔にまとめます。
ステップ3: 経験を交えて一つの記事に統合する
最後に、ステップ1と2で用意したパーツを、一本のストーリーとして繋ぎ合わせます。ここで重要になるのが、Googleが掲げる品質評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)です。
特に、関連トピックを網羅し、ユーザーのあらゆる疑問に答えることは、サイトの専門性と信頼性(E-E-A-T)を高めることに直結します。 しかし、ただ情報を並べるだけでは意味がありません。そこに、あなた自身の「経験(Experience)」を加えてください。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
- 必ず「あなたの会社だからこそ語れる一次情報」をコンテンツに盛り込んでください。
なぜなら、多くの人が網羅性を意識するあまり、どこにでも書いてある情報を並べただけの無味乾燥な「まとめサイト」を作ってしまうからです。AIにも人間にも本当に響くのは、「私たちのサービスを導入したお客様は、こんな風に活用して成果を出しています」「開発担当者に聞いた、ここだけの裏話ですが…」といった、あなた自身の経験や体験談です。それが最大の差別化要因になります。
クエリファンアウトに関するよくある質問
Q. すべての記事をこの形式にリライトする必要がありますか?
A. いいえ、その必要はありません。まずは、あなたのWebサイトで最も重要(コンバージョン率が高い、戦略的に育てたいなど)なサービスやカテゴリのページから着手するのが効率的です。一つの成功事例を作ることが、社内での説得材料にもなります。
Q. サービスページとブログ記事、どちらで対策すべきですか?
A. 両方で対策するのが理想ですが、リソースが限られている場合は「コンバージョンに近い」サービスページから優先的に改善することをお勧めします。ブログ記事は、より広い悩みに答える形でサービスページへ誘導する役割を担うと、サイト全体で効果的な構造を作れます。
Q. 構造化データは必須ですか?
A. 必須ではありませんが、実装することを強く推奨します。構造化データは、AIに対して「この情報は料金です」「これはレビュー評価です」と明確に伝えるための目印のようなものです。実装することで、AIがあなたのサイトの情報をより正確に解釈し、引用してくれる可能性が高まります。
AI時代こそユーザー理解の「王道」が最強の武器になる
本日の要点を3つにまとめます。
AIはユーザーの隠れた疑問(サブクエリ)に答えようとしている。
私たちはその疑問を先回りし、構造的に整理してコンテンツを作る必要がある。
最終的には、あなた自身の経験を交えた「ユーザー理解の深さ」がAI時代のSEOを制する。
「クエリファンアウト」という考え方を、難しく捉える必要はありません。
これからは、お客様一人ひとりが抱える悩みに、より丁寧に向き合うことが大切になる時代です。この記事は、そのための具体的な進め方を示したものです。
まずは、あなたのWebサイトの中で一番重要なページを1つ選んでみてください。
そのページが、お客様の「まだ言葉にはなっていない疑問」にどれだけ答えられているか、一つひとつ確認することから始めてみましょう。
- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?
- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・
- コンサルに頼んでもなかなか改善しない
- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる
大事なのは自社にあったビジネス設計です。
御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します





 シェア
シェア