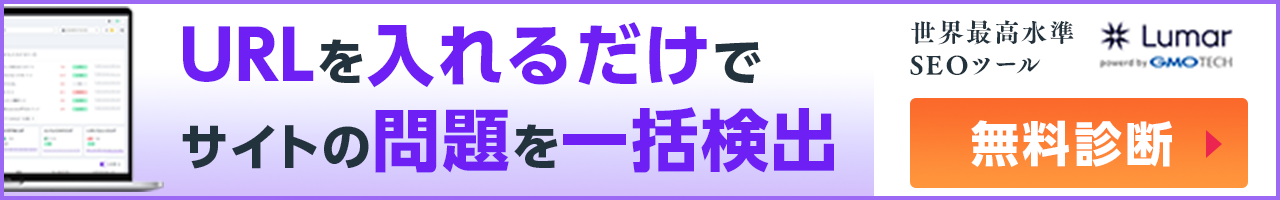Googleの検索順位変動に備えるSEO対策|順位変動を確認する方法と原因

しかし、必ずしもこのアップデートだけが順位変動の判定要因ではなく、「コンテンツの情報」や「検索意図の変化」など様々な要因が関係しています。
ここでは、SEOの変動に影響を与えた「Googleアルゴリズムアップデート」について、また検索順位の変動に関して事前にできる対策や、情報元についても詳しく解説していきます。
- SEOの順位変動に影響した直近のGoogleアルゴリズムアップデート
- November 2021コアアップデート(2021年11月18日~12月1日)
- Link Spam Update(2021年7月26日から)
- コアアップデート(2021年7月2日)
- ページエクスペリエンスアップデート(2021年6月15日)
- スパムアルゴリズムアップデート(2021年6月23日、29日)
- SEOに影響がある変動を事前に知る方法
- Google検索セントラルブログ
- Google関係者や専門家のtwitter
- SEOツールで順位変動を確認する方法
- namaz
- SEMrush
- ahrefs
- SEO対策が原因で検索の順位が変動する理由
- ガイドライン違反
- スパム行為
- セキュリティ
- 検索意図の変化
- コンテンツ情報が古い
- まとめ
SEOの順位変動に影響した直近のGoogleアルゴリズムアップデート
SEOの順位の変動に影響した直近のGoogleアルゴリズムアップデートとして、「November 2021コアアップデート」「Link Spam Update」「コアアップデート」「ページエクスペリエンスアップデート」「スパムアルゴリズムアップデート」の5つがあります。
この5つのGoogleアルゴリズムアップデートの指標によりSEOに影響した内容について紹介していきます。
November 2021コアアップデート(2021年11月18日~12月1日)
「November 2021コアアップデート」は最新のコアアップデートで、2021年11月18日から12月1日に実施されました。
Google公式twitterで発信され、コアアップデートが展開されてから13日後の12月1日に完了したことが、Google公式で報告されています。ちなみにコアアップデートとは、検索アルゴリズムを定期的に見直し、検索結果を大規模に改良することを指すものです。
「November 2021コアアップデート」では、以下の3つ影響が確認されています。
- ツールの順位変動
- 特定のキーワードジャンルの順位変動
- 検索への影響
「November 2021コアアップデート」により、海外を含めたツールの一部で、アップデートによる大きな順位変動が確認されました。また、特定のキーワードのジャンルが大きく順位を下げる変動も確認されています。例えば、「健康と医学」や「IT系」などは順位変動の幅が大きくなっています。
検索への影響が出たのは、海外だけではありません。日本でも、普段から順位が変動しやすいキーワードに関して、大きな変動が確認されました。
Link Spam Update(2021年7月26日から)
「Link Spam Update」は、検索結果の品質向上のために行われています。前回のアップデートは2021年7月26日から展開されました。
このアップデートの目的は、意図的なスパムリンクが行われていないかなど、疑わしいリンクを監視・検知して無効化することです。アップデートによって、今までより広範囲な領域で識別できるようになりました。
過剰な広告リンクやアフィリエイトリンクなど、サイトそのもので収益化を図っている場合は、リンクスパムに関与しているサイトと評価されるようになっています。
コアアップデート(2021年7月2日)
2021年7月2日にも「コアアップデート」が実施されました。その前の6月のコアアップデートの際に対応が間に合わなかった部分が、7月の実施と予告され、実際に行われたものです。
この「コアアップデート」では、「コアアルゴリズムアップデート」と「Core Web Vitals」の2種類が行われました。特定のキーワードのジャンルに大きな順位変動があり、例えば、「健康と医学」や「財務、金融、法律」などに関するキーワードは、順位変動の幅が大きくなっています。
ページエクスペリエンスアップデート(2021年6月15日)
「ページエクスペリエンスアップデート」は、2021年6月15日に展開が開始されました。
このアップデートは、ユーザー体験におけるアップデートのことで、以下のような点が確認されています。
- Core Web Vitalsの追加
- トップストーリーの条件変更
- AMPバッジアイコンの廃止
ページエクスペリエンスでGoogleが重要視しているランキングシグナルは「モバイルフレンドリー」「セーフブラウジング」「HTTPS」「煩わしいインタースティシャルの非表示」でしたが、新たに「Core Web Vitals」が導入されました。
「Core Web Vitals」は読み込み時間(LCP)、インタラクティブ性(FID)、ページコンテンツ(CLS)の3つの点で優れているのかが評価されます。「セーフブラウジング」については、2021年8月にランキングシグナルから使用されていないことが明記され、項目から削除されました。
Googleのトップニュースに掲載されるためにはAMPに対応していることが必須の条件でしたが、このアップデートによりAMP対応は必須条件ではなくなりました。また、これまでAMPコンテンツを示していたバッジアイコンは廃止され、表示されなくなっています。
「ページエクスペリエンスアップデート」による検索順位への影響は、ランキング要因に組み込むためのアップデートも含まれるものです。Googleはあくまでもコンテンツの質を重視していますが、このアップデートにより、少なからずSEOへの影響が確認されています。
スパムアルゴリズムアップデート(2021年6月23日、29日)
「スパムアルゴリズムアップデート」は、2021年6月23日、29日の2回に分けて実施されました。スパム行為のSEO対策を排除して検索結果の品質を保つなど、スパムに対するGoogleの対処の効率性をさらに強化することを意図したものです。
適切なSEO対策をしているサイトであれば、このアップデートにより検索順位が大幅に落ちることは少なく、逆にスパム行為をしているようなサイトが順位を落とすことにより、それ以外のサイトの順位が上がる例もありました。
SEOに影響がある変動を事前に知る方法
SEOに影響がある検索順位の変動については、事前に知ることができます。その情報源としては、主に「Google検索セントラルブログ」と「Google関係者や専門家のtwitter」の2つがあります。
事前にGoogleアップデートの情報がわかれば、どのくらいSEOに影響するのか予測し、対応することもできるでしょう。
Google検索セントラルブログ
SEOに影響がある変動を事前に知る方法に、Google検索セントラルブログがあります。
Google検索のコアアルゴリズムの公式最新情報やGoogle検索の新しい機能についての確認が可能です。Googleが事前に公式の情報を知らせてくれるので、正確に情報を得ることができます。また、日本語翻訳により読みやすくなっていることも、おすすめのポイントです。
Google関係者や専門家のtwitter
SEOの変動に関する情報は、Google関係者や専門家のtwitterで知ることもできます。
Google日本法人の方もtwitterで発信していて、注目すべき情報です。ただし、公式発表ではないため、正確な情報でない可能性もあるので注意しましょう。
SEOツールで順位変動を確認する方法
SEOの順位変動は、ツールを使って調べることができます。順位変動を調べられる主なSEOツールは、「namaz」「SEMrush」「ahrefs」の3つです。
コンテンツなど大きな変更を加えていないにも関わらず、検索順位に変動があった場合は、何らかのGoogleアップデートがあった可能性が考えられます。普段からSEOツールを用いて、変動状況を常に確認しておくことが重要です。
namaz
「namaz(なまず)」は、Google全体の検索順位の変動を知ることができる便利なツールです。「Google平均順位変動幅グラフ」により、検索エンジンの順位変動の状況をリアルタイムで把握することができます。
また、Googleの順位に変動があった場合は、メールで知らせてくれる「変動アラートメール」の機能がついているので、SEO対策にすぐに取りかかることができるでしょう。
SEMrush
「SEMrush(セムラッシュ)」は、ドメイン分析やキーワード調査など、自社や競合サイトのSEO対策に関わる全ての機能が揃っています。また、SEOだけでなく、広告分析やSNS分析などデジタルマーケティングに必要な機能もあります。
SEMrush(セムラッシュ)は記事をサイトに追加した後の順位集計にも便利です。各キーワードの順位経過や上位表示されている記事URLなどを把握することができるので、記事をリライトするなど改善が必要な記事や構成を見つけ出すことができます。
ahrefs
「ahrefs(エイチレフス)」は全世界で利用されているツールです。ライバルサイトの情報を分析できる機能や、キーワード検索機能があるため、コンテンツ設計の手間を省くことができます。
なかでもよく使用されている機能の一つが、「被リンクの獲得数調査」です。期間ごとに被リンク参照ドメインの数を確認することができます。また、「オーガニック検索」という機能で検索順位を確認することも可能です。自動でキーワードを抽出し、トラフィック上位順にキーワードを表示してくれます。
SEO対策が原因で検索の順位が変動する理由
アルゴリズムのアップデート以外でも、SEO対策が原因で検索の順位が変動する場合があります。
その理由として主に挙げられるのが、「ガイドライン違反」「スパム行為」「セキュリティ」「検索意図の変化」「コンテンツ情報が古い」の5つです。それぞれの注意点と対策を押さえておきましょう。
ガイドライン違反
Googleのガイドラインに違反したコンテンツをサイトに掲載すると、そのコンテンツやサイト全体の評価を下げてしまいます。最悪の場合、インデックスから削除されて、検索結果に表示されなくなってしまうかもしれません。
例えば、自社サイトに向けられた不自然なリンクがあるときは、要注意です。自分が意図していなくても、リンクを向けられた自社サイトが違反を犯しているとみなされてしまう可能性もあります。不自然なリンクを見つけたら、まずは自分で調査し、必要に応じて削除して再審査リクエストを申請しましょう。
スパム行為
スパムに該当するような行為でも、検索の順位が変動します。
スパム行為とは、検索エンジンを偽りだますような手法です。例えば、検索エンジンとユーザーにそれぞれ異なるページを見せるクローキングをしていたり、コンテンツに関係ないキーワードをページ内に埋め込んでいたりする行為が、スパム行為にあたります。
このような手法でサイトやページを作っていれば、Googleでは違反とみなされ、評価が悪くなってしまうでしょう。そのため、自社サイトのコンテンツにスパム行為に該当することが行われていれば、その部分の削除や修正をする必要があります。
セキュリティ
Webサイトがセキュリティの脅威にさらされている場合にも、検索順位が変動する可能性があるため要注意です。
セキュリティが脆弱なWebサイトは、検索ユーザーがページに移動する前に警告を表示することがあります。この場合、検索トラフィックが減少し、結果として検索順位が下がってしまうのです。
そのため、自社サイトのセキュリティ面には常に気を配っておくことが求められます。
検索意図の変化
検索順位が変動する理由としては、ユーザーの意図が変化してきた場合も挙げられます。一度上位表示されたコンテンツであっても、時間とともにユーザーの興味・関心が変化すると、突然順位が下降することもあるため注意が必要です。
このような場合の対策としては、以下のことを心がけましょう。
- 常に上位表示されているコンテンツをチェックすること
- 検索ユーザーの知りたい傾向を調べること
上記のことを意識して、現在のユーザーに合ったコンテンツをリライトする必要があります。ユーザーの検索意図を調べるには、「キーワードサジェストリサーチツール」「ラッコキーワード」「Googleキーワードプランナー」「ヤフー知恵袋」でのリサーチがおすすめです。これらのツールを利用することで、ユーザーの現在の検索傾向を知ることができます。
コンテンツ情報が古い
コンテンツの情報が古いと、検索順位が下がってしまうことがあります。なぜならGoogleは、常に新しい情報を掲載しているサイトを評価する傾向があるからです。
コンテンツが掲載されて1年以上経つと、その情報に関する状況が変化し、場合によっては間違った情報を伝えてしまうことにもなりかねません。また、ページレイアウトに関しても、古いものだとユーザーは見にくく、利便性を下げる原因となります。
常に最新の情報となるように追記、修正し、ユーザーにとって使いやすく、見やすいコンテンツの掲載を心がけましょう。
まとめ
ここまで、Googleの順位変動でSEOに影響した直近のアルゴリズムアップデートや、順位変動が起きる原因、対策について解説してきました。
アルゴリズムアップデートは大きく順位を変動させる要因ではありますが、ツールなどを利用して事前に察知しておくことで、ある程度は備えることが可能です。また、検索順位の変動はSEO対策によっても影響を最小限に抑えられます。
普段から「コンテンツの質」を高めることを意識して、SEO対策を行っていきましょう。
- SEO対策でビジネスを加速させる「SEO Dash! byGMO」
-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?
- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・
- コンサルに頼んでもなかなか改善しない
- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる
大事なのは自社にあったビジネス設計です。 御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

 ツイート
ツイート シェア
シェア