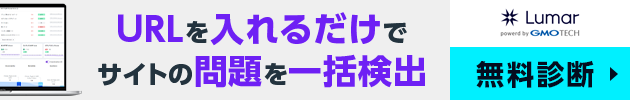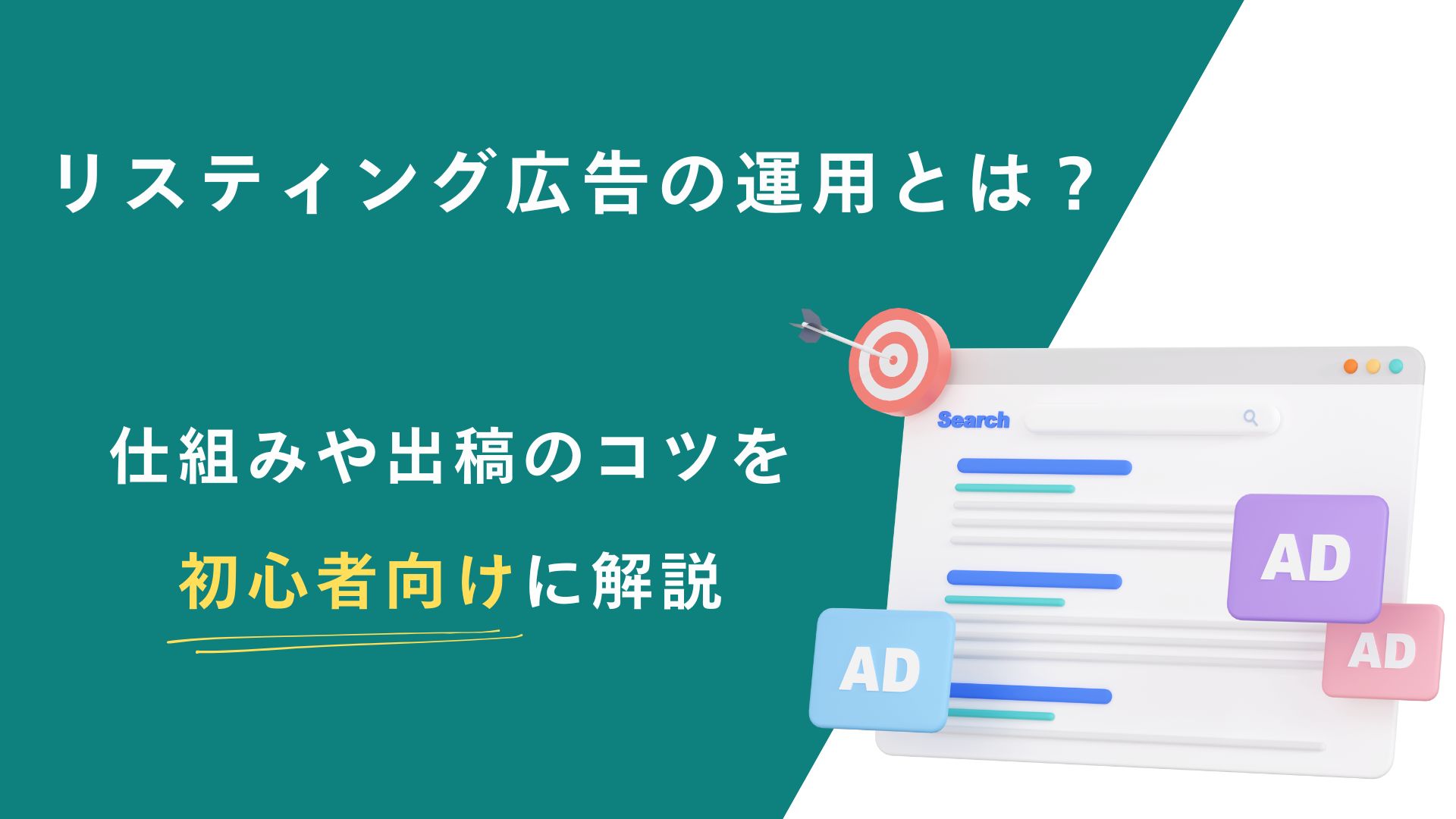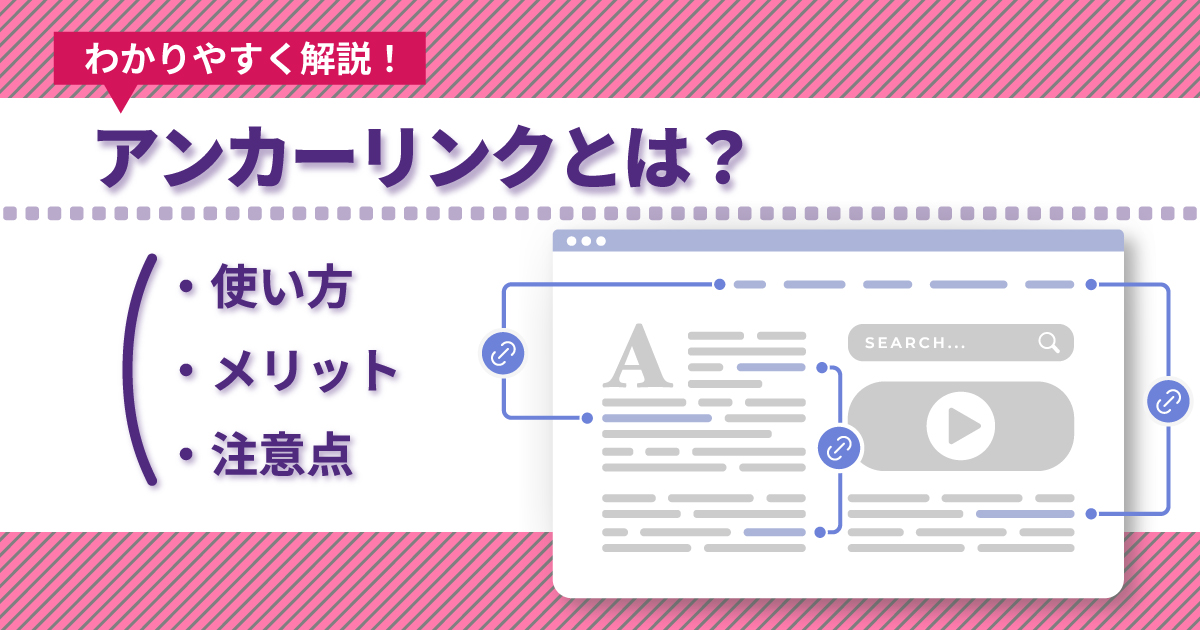ペンギンアップデートとは?導入された背景とSEOへの影響を解説

Googleでは定期的にアップデートを行っていますが、実際に何がどのように変わったのかまで詳しく把握できている方は多くありません。
ペンギンアップデートでは、主にスパム行為や低品質な被リンクを対象にペナルティが課されました。このペンギンアップデートにより、多くの悪質なサイトが検索順位を下げることになったのです。
今回は、この先またアップデートが行われた際に不本意にペナルティを受けてしまうことのないように、ペンギンアップデートの概要や導入された背景・SEOへの影響について詳しく解説していきます。
- SEOに悩むサイト担当者必見!世界最高水準のテクニカルSEOツール「Lumar」
-

URLを入れるだけでサイト内部の問題を一括検出。
Googleと同じ視点でサイトクロール、
大規模サイトでも手軽に高度なSEO分析ができます!まずは無料デモクロールを試して、あなたのサイトの問題点を一括検出!
ペンギンアップデートとは?
ペンギンアップデートとは、ランキング操作を目的としたリンク構築やスパム行為を行うサイトを排除して、検索結果の品質を高めるために行われたアルゴリズムのアップデートです。
ランキング操作を目的としたユーザーの役に立たない低品質なサイトの順位を下げ、ユーザーにとって役に立つ良質なサイトを上位表示することを意図している点は、パンダアップデートと同じになります。
ペンギンアップデートの名前の由来は、パンダアップデートと同じく「サイトの質を白黒ハッキリさせる」という意味で、白黒配色が印象的なペンギンの名前が付いたと言われています。
Googleガイドラインで禁止されている「スパム行為」に対してペナルティを課し、そのサイトの検索順位を下げたり検索結果から削除したりしました。
このペンギンアップデートはGoogleの「コアアルゴリズム」にも組み入れられ、現在も違反行為をするサイトを厳しく取り締まっています。
ペンギンアップデートが導入された時期と理由は?
ペンギンアップデートは、2012年4月に導入されました。
ユーザーの役に立たない低品質なサイトでも、リンク本数が多ければ検索上位に表示されていた状況を打開するために取り入れられたのです。
実際に2012年ごろまでのSEO施策は「コンテンツの質よりもリンク本数を重視する施策」が主流だったので、むやみにリンクを集めた低品質なサイトがランキング上位を独占し、ユーザーの役に立つような検索結果を表示できていませんでした。
ペンギンアップデートでは「リンクの質に関する評価」を見直し、低品質なリンクを受けているサイトの順位を下げています。この仕様は現在でも残っており、リンクの質は検索結果に大きく影響すると言われています。
パンダアップデートとはペナルティの対象が異なる
ペンギンアップデートは、パンダアップデートとはペナルティの対象が異なります。ペンギンアップデートは「SEOスパムと低品質な被リンク」を対象にしているのに対し、パンダアップデートは「低品質なコンテンツ」を対象にしていました。
パンダアップデートでは、無断複製されたコンテンツや中身のないコンテンツなど低品質なコンテンツがターゲットとされて、ペナルティを課されたのです。
ペンギンアップデートもパンダアップデートも、共にユーザーの利便性を考慮しないランキング操作目的のサイトに対して行われたアップデートとしては同じです。
逆に言えば、どちらのアップデートもユーザーの役に立つ高品質なサイトであれば、その分評価されて検索順位を上げることに繋げられます。
ペンギンアップデートの具体的な内容
- リンクプログラムへの参加
- 自動生成されたコンテンツからのリンク
- クローキング
- 不正なダイレクト
- 隠しテキストや隠しリンク
- コンテンツに関係のないキーワードをページに詰め込む
- リッチスニペットマークアップを悪用する
ペンギンアップデートは、具体的に次のようなサイトに対してペナルティを課しました。
上記のような「スパム行為や低品質な被リンク」は、Googleガイドラインに違反対象として書かれています。
引用元:品質に関するガイドライン|Google検索セントラル
リンクプログラムへの参加
リンクプログラムに参加しているサイトは、ペナルティの対象になりました。リンクプログラムは検索ランキングを意図的に操作するために行うものだからです。
例えば、次のようなサイトが挙げられます。
- リンクの売買やリンク設定に対する謝礼品のやり取りなどを行い、被リンクを増やす
- 過剰な相互リンク(リンクを張る代わりに相手にもリンクを張ってもらう)や相互リンク目的のパートナーページを作成する
- テキストリンクに上位表示させたいキーワードを含めて、大量にリンクを張ってもらう
- 自動化されたプログラムやサービスを使用して自分のサイトへのリンクを作成する
Googleは、上記のような行為を全てリンクプログラムとみなし、厳しく対応しています。
自動生成されたコンテンツからのリンク
自動生成されたコンテンツからリンクを張る行為も、厳しい評価を受けています。自動生成されたコンテンツはユーザーの役に立たないコンテンツとみなされているため、そのようなサイトにリンクされる行為もランキング操作を目的としていると認識されてしまうからです。
実際に自動生成されたコンテンツは、ワードサラダなどを利用した意味のない文章を組み合わせたコンテンツのことが多いです。このようなユーザーの役に立たない低品質なコンテンツが、パンダアップデートの対象になりました。
これがペンギンアップデートの際には範囲が広がり、サイト自体の内容に問題がなくても、上記のように低品質なサイトにリンクされているサイトもペナルティの対象となっています。
クローキング
ユーザー(人間)と検索エンジンに対して、それぞれ異なるコンテンツまたはURLを表示する「クローキング」を行っているサイトもペンギンアップデートの対象となりました。
クローキングの主な手法は、次のようなものが挙げられます。
- 検索エンジンにはHTMLテキストのページを表示し、ユーザーには画像のページを表示する
- ページリクエストしたユーザーが人ではなく検索エンジンである場合のみ、ページにテキストやキーワードを挿入する
上記のように、クローキングされるとユーザーの検索意図と関係のないテキストや画像が表示されます。検索結果でこのようなことが起こると、ユーザーの悩みを解決するどころか検索エンジンに対して不信感を抱きますよね。
不正なリダイレクト
不正なリダイレクトは、ユーザーが予期しないことが起こるため偽装行為に当たります。リダイレクトとは、サイトにアクセスしようとするユーザーを最初にアクセスしたURLと別のURLに移動させることです。
時には、サイトのURLを変更した時や複数のサイトを1つのページに統合したときなど、正当な理由で行われるケースもあります。
しかし、ユーザーを不本意に別サイトへ誘導するような不正なリダイレクトは、ランキング操作が目的の悪質な手法です。不正なリダイレクトは、クローキングと同じようにユーザーのことを無視したスパム行為とみなされ、検索順位を大きく下げます。
隠しテキスト・隠しリンク
ユーザーには気づかれないようにして検索エンジンにだけ読み込ませることを目的とした「隠しリンク」や「隠しテキスト」は、偽装行為としてペナルティの対象になりました。
隠しテキストや隠しリンクは、ユーザーにはわからないような手法で挿入されています。
- 白の背景で白のテキスト
- テキストを画像の背後に置く
- CSSを使用してテキストを画面の外に配置する
- フォントサイズを0にする
- 小さな1文字(段落中のハイフンなど)のみをリンクにする
上記のように検索エンジンにだけわかるようにキーワードやリンクを挿入しているので、検索キーワードとは全く関係のないページが表示される可能性があります。
このようなユーザーを騙す行為はGoogleの理念に背いているので、厳しいペナルティが課されるという訳です。
コンテンツに関係のないキーワードをページに詰め込む
コンテンツに関係のないキーワードをページに詰め込む行為も、ペナルティの対象になりました。コンテンツ内に過剰にキーワードを詰め込む行為は、ランキングに悪影響を及ぼす可能性があるからです。
Googleの検索ランキングを操作する目的でWebページにキーワードや数字を詰め込む行為を「キーワードの乱用」と言います。キーワードの乱用は、不自然な文章でキーワードを無理矢理に詰め込む傾向があります。つまり、ユーザーにとって役に立つ記事とは言えません。
リッチスニペットマークアップを悪用する
ペンギンアップデートでは、リッチスニペットマークアップを悪用した手法がペナルティの対象になりました。これもまたユーザーを騙す悪質な行為だからです。
リッチスニペットとは、検索結果画面でWebページのタイトルの下に書かれているページの説明文のことです。このリッチスニペットを読んで「この記事を読んでみよう」とアクセスするサイトを選ぶ基準にしている人も多いでしょう。
リッチスニペットマークアップの悪用とは、このリッチスニペットに実際のページの内容とは異なる説明文を載せることです。「この記事を読んでみたい」と思わせたユーザーを騙す行為と言えますよね。
このようなユーザーに対する偽装行為は、ペンギンアップデートによって姿を消すことになりました。
Googleのガイドラインに準拠していることがSEOには重要
SEO対策では、Googleのガイドラインに準拠していることが重要と言えます。ホワイトSEOを行い、「コンテンツSEO」に取り組むことが検索上位に表示される近道だからです。
この記事で解説したように、ペンギンアップデートによってブラックハットSEOは衰退しました。
コンテンツSEO、すなわちユーザーの検索意図に沿った良質なコンテンツを作成しなければ、検索上位に表示されることはありません。
さらに、良質な被リンクを増やしたりXMLサイトマップを設置したりするなど、ユーザーだけではなく検索エンジンのクローラーにも読みやすくする必要があります。
まとめ
ペンギンアップデートの概要や導入された背景、また具体的なアップデートの内容について解説しました。
ペンギンアップデートによって、スパム行為や質の低い被リンクが厳しく取り締まられています。つまり、小手先の技を使うようなブラックハットSEOには効果がなくなり、いまはコンテンツSEOの時代になったということです。
これからは、「どうしたらユーザの役に立つコンテンツになるのか」を重視した、Googleの理念に沿った「ユーザーファーストのコンテンツ作り」が大切と言えます。
- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?
- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・
- コンサルに頼んでもなかなか改善しない
- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる
大事なのは自社にあったビジネス設計です。
御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

 ツイート
ツイート シェア
シェア