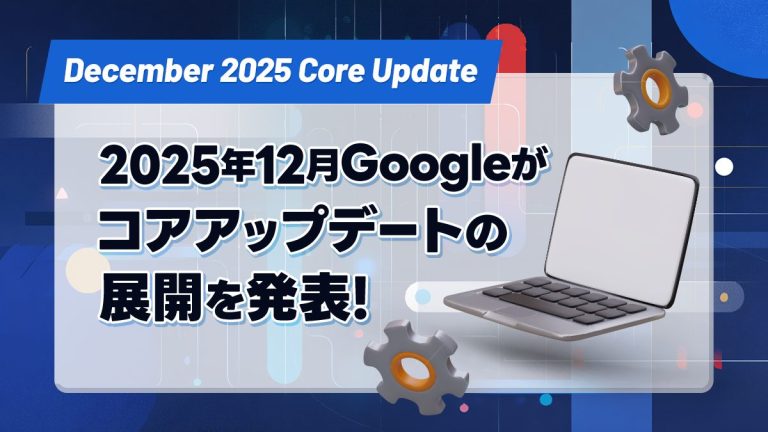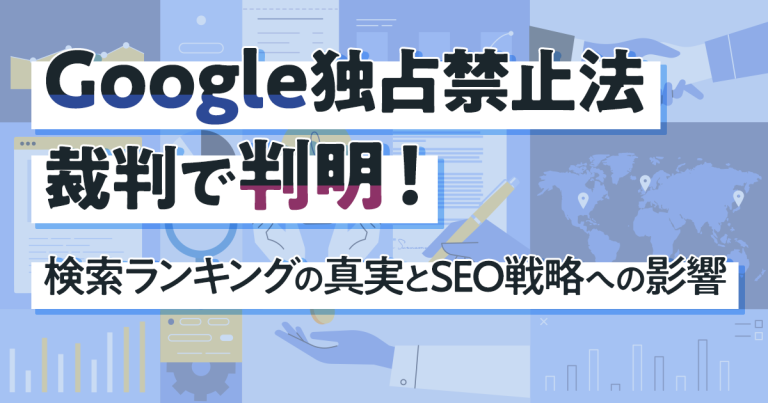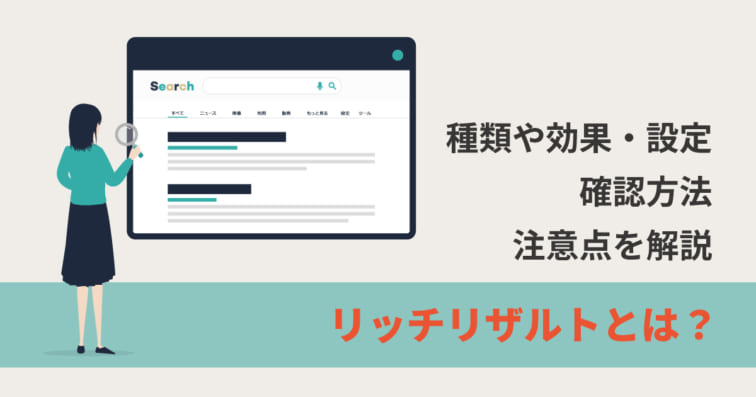【実行プラン付】LLMO対策とは?AI時代に成果を出すWeb戦略と9つの具体的施策

LLMO対策とは、AIによる検索の変化に対応し、企業の専門性をWeb上で証明する新たなSEO戦略です。
本記事では、日々のアルゴリズム研究とSEOの支援実績から導き出した、トラフィックを維持・向上させるための具体的な9つの施策と、経営層への報告にも使える実行計画を解説します。
この記事を読めば、以下の3点が明確になります。
- LLMOの基礎知識と、従来のSEOとの決定的な違い
- 明日から着手できる、具体的なLLMO対策9選
- 対策の成果を測り、中長期的な戦略を立てる方法
LLMO対策とは?今さら聞けない基本とAI時代の必要性
👉 このパートをまとめると!
- LLMOとは大規模言語モデル最適化のこと。AI検索での表示を目指す施策で、検索プロセスが新たに構築される時代の必須戦略です。
そもそもLLMO(大規模言語モデル最適化)とは?
「LLMO」という新しい言葉を目にし、自社のWeb戦略はどう変わるべきかと情報収集されている方も多いでしょう。LLMOとは「Large Language Model Optimization」の略で、日本語で「大規模言語モデル最適化」を意味します。
これは、Googleの「AI Overviews」に代表されるような、AIが生成する回答の中に、自社の情報やサイトへのリンクを引用してもらうことを目指す一連の施策を指します。
従来のSEOが「検索順位で1位を目指す」施策だったとすれば、LLMOは「AIの回答に採用される」という、まったく新しい施策なのです。
なぜ今、LLMO対策が重要なのか?
LLMO対策が急務である本質的な理由は、単に「AI Overviews」という新機能が登場したから、というだけではありません。より根本的な地殻変動、すなわち「検索し、サイトを閲覧する」という、私たちが慣れ親しんだ情報探索のプロセス全体が、生成AIを中心に再構築されつつあるからです。
これまでのWebの世界では、ユーザーは検索エンジンが提示するWebサイトのリストを「直接」訪れていました。 しかし、AI時代には、ユーザーはAIとの「対話」を通じて、複数の情報源からAIが合成・要約した答えを受け取るようになります。
この変化において、個々のWebサイトは、AIの回答を構成するための「間接的な情報ソース」という役割へと変わっていくのです。
この新しいエコシステムで影響力を失わないためには、もはや自サイトへのクリックを待つだけでは不十分です。いかにしてAIに「信頼できる情報源」として認識され、その回答の中に自社の知見を引用してもらうか。この問いに答えるための活動こそが、LLMO対策の核心となります。
その象徴的なデータとして、海外の調査では、AIが回答を提示した場合、従来の検索結果へのクリック率が著しく低下する可能性も示唆されています。言い換えれば、新たなプロセスに適応できない企業にとって、ユーザーとの接点を失うリスクがあるということです。
SEO・AIOとの違い
LLMOと合わせて、「AIO(AI Optimization)」という言葉も聞くかもしれません。これらの関係性を整理しておきましょう。
- SEO (検索エンジン最適化)
- LLMO (大規模言語モデル最適化)
- AIO (AI最適化)
人間が検索するキーワードに対し、Webページを上位表示させるための施策
AIの生成する「回答」に自社情報を引用させるための施策
LLMOを含む、AI時代の検索体験全般に対する最適化活動の総称
つまり、AIOという大きな枠組みの中に、LLMOや従来のSEOが含まれるイメージです。まずは、AIの回答に焦点を当てた「LLMO対策」から着手することが、最も現実的で効果的な一手となります。

明日から始めるLLMO対策ロードマップ9選
👉 このパートをまとめると!
- 専門性と信頼性をAIに伝えるため、「E-E-A-Tの証明」「技術的対応」「コンテンツ戦略」の3軸で、具体的な9個のアクションプランを段階的に実行します。
ここからは、「理論は分かったが、具体的に何をすればいいの?」という読者のみなさんの疑問にお答えします。私が日々のアルゴリズム研究・自社メディアによる効果検証・クライアント支援の中で効果を実感した、具体的かつ実行可能な9つの施策をロードマップ形式でご紹介します。
【ステップ1】E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の証明
AIは、情報の「正しさ」を担保するために、その情報が「誰によって」発信されたかを重視します。まずは、自社の専門性をWeb上で証明する土台を固めましょう。
①著者・監修者情報を全記事に実装する
コンテンツの信頼性は、その書き手によって大きく左右されます。すべての記事に、誰が・どんな専門性を持って書いたのかを明記する「著者情報」を必ず設置してください。
✍️ 中原の経験から一言アドバイス
- 著者プロフィールには「顔写真」「氏名」「所属・役職」「簡潔な実績」「関連SNSリンク」の5項目を必ず含めてください。その結果、信頼性が飛躍的に向上すると考えられます。
ご支援するメディアの中には、2025年3月のコアアルゴリズムアップデート以降、著者プロフィールを充実させたことで、すべてのコンテンツの平均掲載順位が5位以上も上昇した事例もあります。
②About Usページ(自社について)を徹底強化する
AIは、貴社がどのような企業なのかを理解するために、間違いなく「About Us」ページを参照します。この部分の内容が乏しいと、企業としての実在性や信頼性が疑われかねません。会社の沿革、事業内容、受賞歴、企業理念、所在地など、自社の実体を証明する情報を網羅的に記載し、定期的に更新しましょう。
③一次情報・独自調査をコンテンツに含める
他サイトの情報をまとめただけの記事は、もはやAIにとって価値がありません。自社で実施したアンケート結果、顧客へのインタビュー、独自の市場調査など、自社でしか持っていない一次情報こそが、AIに引用される最高のフックとなります。
他の調査を参考にする際は、剽窃を避けるためにも、例えば「〇〇社の調査によれば~」と出典を明確にした上で、そこに自社独自の解釈や考察を加えることが極めて重要です。
【ステップ2】AIが読み取りやすい技術的対応
次に、AIという機械が、ご自身のサイトの情報を正確に理解するための技術的な設定を行います。まずは、今すぐ実行できることから始めましょう。
④構造化データ(FAQ, How-to等)をマークアップする
構造化データとは、ページのコンテンツが「これは質問です」「これは手順です」といった意味を持つ情報であることを、AIに正確に伝えるための特殊なコードです。特にFAQ(よくある質問)やHow-to(手順)の構造化データは、AIが回答を生成する際に直接参照しやすいため、積極的に実装しましょう。
⑤Wikipediaや公式サイトで「エンティティ情報」を確立する
AIは、単なる文字列ではなく「エンティティ(固有の概念)」で世界を認識しています。自社名や製品・サービス名が、信頼できる情報源(特にWikipediaや業界団体の公式サイト)で一つのエンティティとして確立されると、AIからの評価が格段に高まります。
✍️ 中原の経験から一言アドバイス
- Wikipediaでの自社ページ作成はハードルが高いですが、まずは「業界団体への加盟」「公的機関発行の資料への掲載」「権威あるメディアでの受賞」を目指すのが現実的な第一歩です。
実際に私が支援したあるBtoB企業では、業界紙のアワードを受賞し、その情報が公式サイトに掲載されたことで、AIによる企業名の認識精度が向上した事例があります。
【注目】AIクロール制御の新たな動き
現在、robots.txtがクローラー制御の標準ですが、将来的にはAIに特化した、より詳細な制御方法が登場する可能性があります。その一つとしてllms.txtのような仕様が議論されています。
ただし、2025年6月現在、この仕様は主要なAI提供企業に正式採用されてはいません。
今すぐに何かをする必要はありませんが、「AIとの対話方法」に関するこうした新しい技術動向にもアンテナを張っておくと、将来競合に先んじて対応できるでしょう。
【ステップ3】AIに引用されるコンテンツ戦略
最後に、AIに「引用したい」と思わせるコンテンツの作り方です。
⑥網羅的なトピックより「問いに直接答える」コンテンツを作る
AIは、ユーザーの特定の疑問(クエリ)に対して、最も的確な答えを探しています。そのため、ページ全体が「一つの問い」に特化している方が、AIにとって「この記事はこの質問の専門ページだ」というシグナルが明確になります。
✍️ 中原の経験から一言アドバイス
- まずGoogle AnalyticsでPV数トップ10の長文記事(ハブ候補)を特定します。その中で、単体でも一つの充実した専門記事に発展させられる章(スポーク候補)を見つけてください。
その章を単に分割するのではなく、より多くの具体例、図解、関連FAQを加えて情報を拡充・深化させ、独立した専門記事として公開します。
最後に、元の記事(ハブ)と新しい記事(スポーク)を相互にリンクさせ、「トピッククラスター」を形成することで、サイト全体の専門性をAIに示します。LLMO対策を加速させるための「戦略的コンテンツ分割」です。

⑦記事内に「〇〇氏によると」と専門家の発言を引用する
自社の主張を補強するために、外部の権威ある専門家の見解を引用することも有効です。例えば、著名なアナリストの言葉を引用することで、記事全体の信頼性が向上します。 その際は、著作権法を遵守し、引用部分を <blockquote> タグで明確に区別し、出典を必ず明記してください。
⑧YouTube動画で「How-to」を解説する
Googleは、AIの回答ソースとしてYouTube動画を積極的に利用しています。特に、何かを実演する「How-to」系のコンテンツは動画との相性が抜群です。製品の使い方やサービスの導入手順などを動画で解説し、そのタイトルや説明文、字幕を最適化することで、新たな引用機会が生まれます。
⑨プレスリリースで企業の公式見解を発信する
プレスリリースは、企業としての「公式発表」であり、AIはこれを信頼性の高い情報源として扱います。新サービスの発表や経営に関する重要なお知らせなど、公式見解をプレスリリースとして発信することは、間接的ながら非常に効果的なLLMO対策となります。
LLMO対策の効果測定と中長期的な考え方
👉 このパートをまとめると!
- 効果測定は「被引用」の概念を理解した上で、AI Overviewsでの表示状況やブランド指名検索数の推移を追うことが重要です。
ここまで具体的な施策を解説してきましたが、きっと「では、これらの効果はどうやって測ればいいんだろう?」と思っているはずです。
正直に申し上げると、現時点でLLMO対策のROI(投資対効果)を正確に測定する完璧な方法はありません。
しかし、先手を打っておいて何も損はありません。
現状で可能な効果測定の方法
完璧なツールはありませんが、対策の方向性を占うことは可能です。
まず念頭に置くべき新しい考え方が、従来の「被リンク」に代わる「被引用(サイテーション)」という概念です。これは、AIや他サイトにどれだけ信頼できる情報源として「引用・言及されたか」を重視しています。
その上で、現状で可能な具体的な観測指標として、以下の2つが挙げられます。
- AI Overviewsでの表示状況
- ブランド指名検索数の推移
自社の主要キーワードで検索し、AIの回答に自社サイトが引用されているかを目視で定期的にチェックします。
AIに頻繁に引用されるようになれば、企業の認知度が高まり、会社名やサービス名での直接検索(ブランド指名検索)が増加するはずです。これはGoogle Search Consoleで確認できます。
LLMO時代のSEOの本質とは?
様々なテクニックをご紹介しましたが、最後に最も重要なことをお伝えします。
LLMO対策の究極のゴールは、小手先のテクニックを弄することではなく、「このテーマで最も信頼できるのは、この会社だ」とユーザーとAIの両方に認めてもらうことです。
私は15年間、数えきれないほどのGoogleアルゴリズムの変動を経験してきましたが、常に生き残ってきたのは、顧客の課題と真摯に向き合い、自社の経験を基に本物の価値を提供し続けてきたサイトだけです。AIという新しいプレーヤーが登場しましたが、この「価値提供」という本質は決して変わりません。
LLMO対策に関するよくある質問(FAQ)
👉 このパートをまとめると!
- LLMO対策は中小企業にこそチャンスがあり、全コンテンツの修正は不要。自社の強みが活かせる領域から着手するのが成功の鍵です。
Q. 中小企業でもLLMO対策はやるべきですか?
A. むしろ、中小企業にこそ大きなチャンスがあります。大企業がカバーしきれないニッチな領域で、誰にも負けない専門性を発信し続ければ、その分野の第一人者としてAIに評価される可能性が十分にあります。
Q. 既存のコンテンツはすべてリライトが必要ですか?
A. その必要はありません。まずは、貴社のビジネスに直結する重要なサービスページや、すでに多くのアクセスを集めているブログ記事など、影響の大きいページから優先的に対策を始めるのが最も効率的です。
Q. 効果が出るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
A. これは一概には言えません。しかし、一夜にして効果が出る魔法の杖ではないことは確かです。従来のSEOと同様、最低でも3ヶ月から半年は腰を据え、中長期的な視点で継続的に取り組むべき施策とお考えください。
まとめ:AI時代を勝ち抜くWeb戦略の第一歩
本記事では、LLMO対策の基本から、明日から着手できる9つの具体的な施策、そしてその効果測定の考え方までを解説しました。
- LLMO対策は、AIに仕事を奪われる脅威ではなく、自社の本物の専門性を示す新たな機会です。
- まずは本記事で紹介した9つの施策をチェックリストとして、一つでもできることから始めてみてください。
- そして最も重要なのは、テクニックに溺れず、常に「読者の課題を解決する」というコンテンツ作りの本質に立ち返ることです。
この記事が、ご自身の会社のWeb戦略を、AI時代に適合した、より力強いものへと進化させるための一助となれば幸いです。
- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?
- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・
- コンサルに頼んでもなかなか改善しない
- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる
大事なのは自社にあったビジネス設計です。
御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します





 シェア
シェア