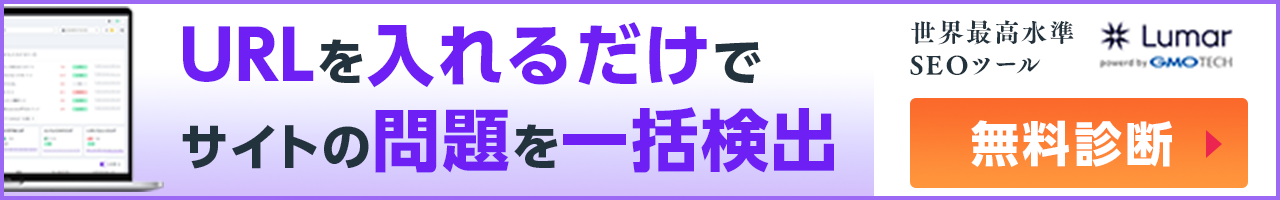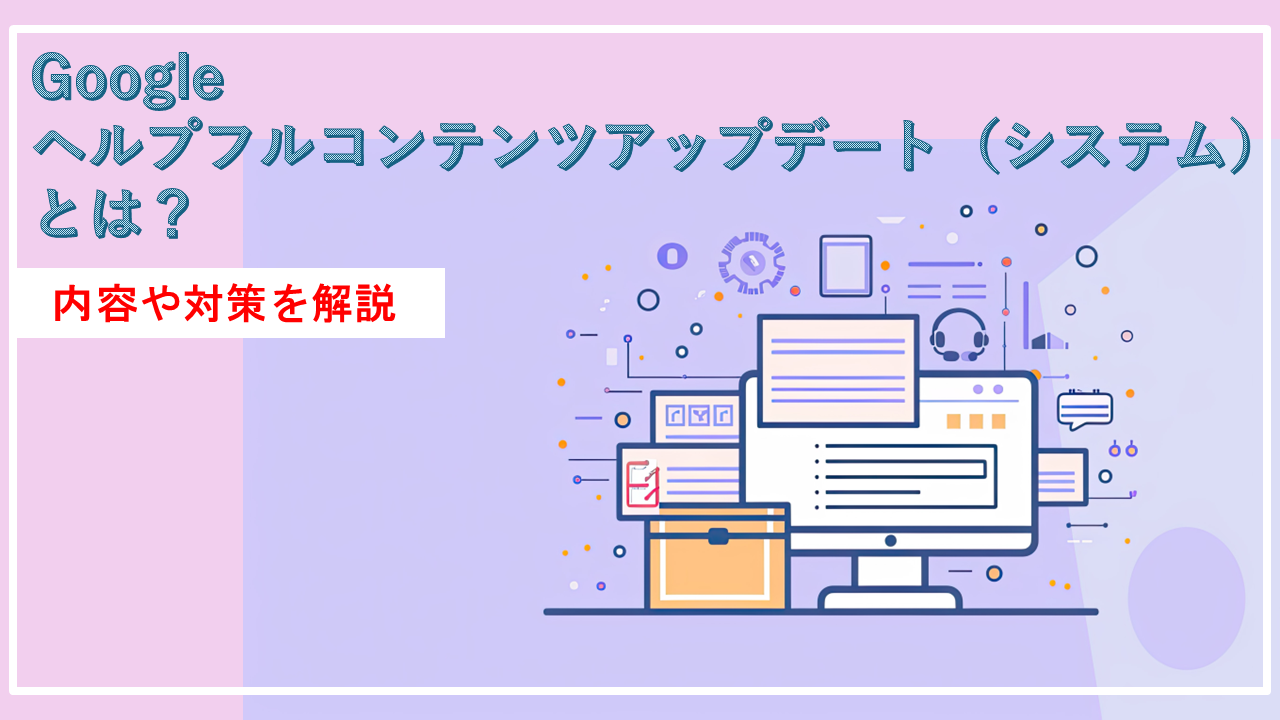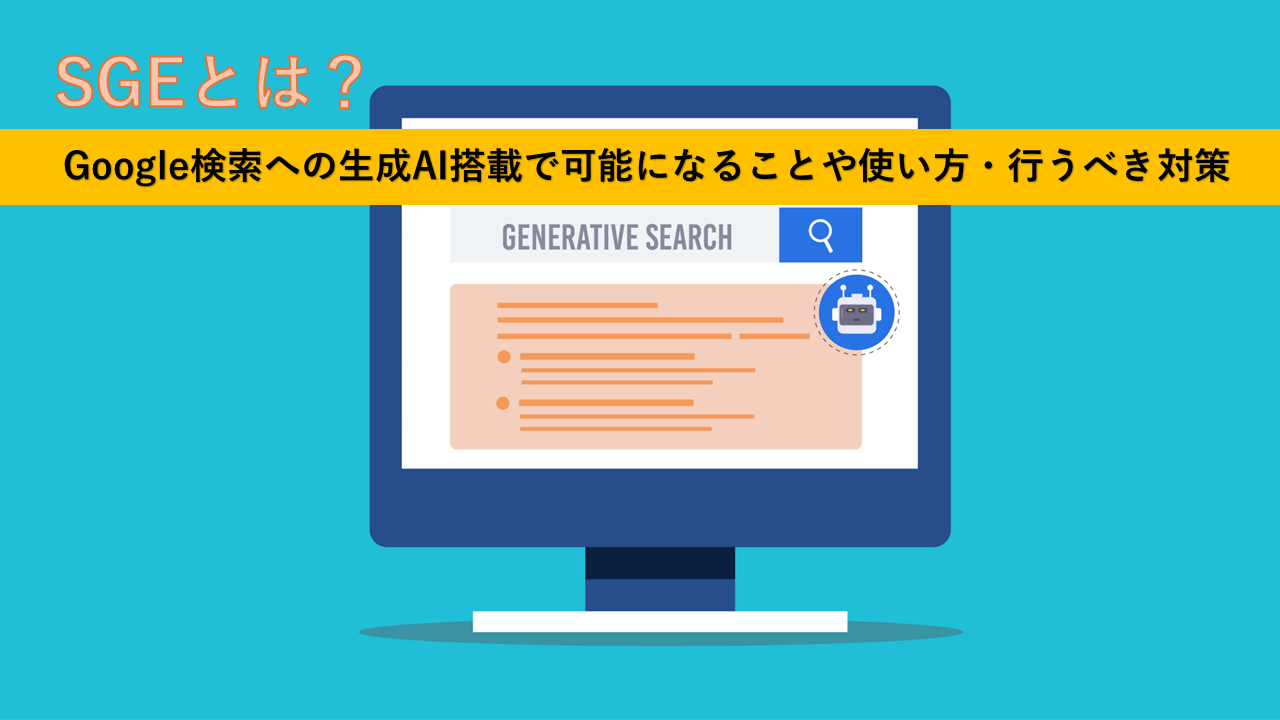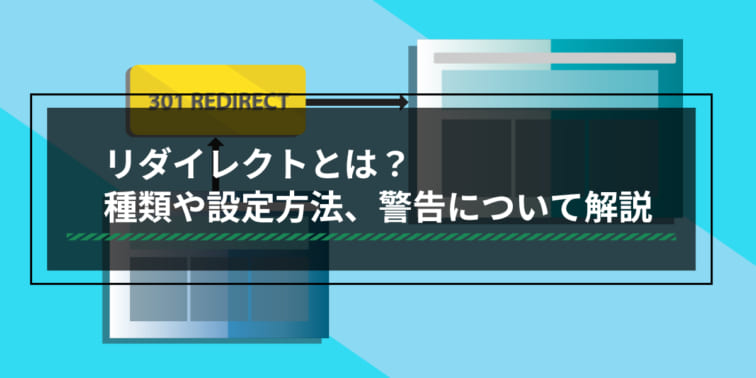SEOと文字数の関係性とは?検索順位を上げるコンテンツのポイントや注意点を解説

本記事では、SEOと文字数の関係性と長文コンテンツの作成方法について解説します。
文字数とSEOに関係性はある?
SEOとコンテンツの文字量には直接的には関係性はありません。なぜなら、文字数を検索上位の決定要因とするアルゴリズムがないからです。
実際、Googleのジョン=ミュラー氏はこの件について以下のように公言しています。
【翻訳】
Googleは「100文字に満たないすべてのページは悪い、文字数100~500程度が大丈夫で、500以上は5枚の画像がないといけない」と言ったようなページの文字数を数えるアルゴリズムを持っていない。
Googleはページの全体を評価し、ユーザーにとって有益で関連性の高いコンテンツであれば、コンテンツの長さや画像の有無は全く関係ない。
English Google Webmaster Central office-hours hangout
このことからもわかるように、Googleの検索エンジンは検索ユーザーに最も関連性の高いコンテンツを上位表示します。したがって、例えばSNS上で掲載された短文であっても、ユーザーにとって有益で満足を満たす情報であれば上位表示されるのです。
しかしながら、実際の検索上位の記事は文字数が多いコンテンツが多くを占める傾向にあります。そういった意味では、文字数は直接的な影響はありませんが、間接的には影響するといえます。
文字数がSEOに「間接的」に影響する理由
Googleは文字数の量をコンテンツ評価の指標にはしていません。重視しているのはユーザーが必要とする情報を満たすコンテンツです。ユーザーは抱える疑問を解決できること期待して、検索エンジンにキーワードを入力します。
そして、コンテンツを読み終えたら検索行為を終了できるくらいの情報の網羅性が高いコンテンツを切望しています。コンテンツはこの期待に応えなければいけません。
そのため、コンテンツを作成する側はユーザーが知りたい情報でなかったり、信用できない内容にならないように情報の粒度を高めなければいけません。すると、必然的に情報の幅広さや深さが必要になるため、文字数も多くならざるを得ません。
文字数が多くなるのは、コンテンツの質を追い求めた結果起きる現象と言えるでしょう。
最適な文字数とは
最適な文字数は検索キーワードによって異なります。
例えば、「8月 北海道 気温」と検索エンジンに入力したユーザーが知りたいことは、8月の北海道の気温や天気だけでなく服装や持ち物についても知りたいのです。
これは検索結果の上位記事から読み取れます。このキーワードの場合、盛り込むべきトピックが多岐に渡るため、文字数もある程度必要になってきます。
一方、「沖縄市 天気」 で検索すると、検索結果には沖縄市の天気や気温を端的に回答する情報が表示されます。沖縄の天気について環境問題の観点から論じた長文などは上位コンテンツにはありません。
検索キーワードよってコンテンツの回答性は端的であったり、詳細であったりとケースバイケースです。文字数にこだわらず、あくまでもユーザーの疑問に過不足なく回答した結果でしかないと意識しておくくらいでよいでしょう。
それでもなお文字数の目安を知りたい時は、検索上位の競合コンテンツを参考して割り出しましょう。または、ツールを使う方法もあります。
文字数の多いコンテンツのメリット
結果的に長文になったコンテンツは上位表示される傾向があります。メリットは以下の通りです。
- ユニーク単語が増える
- 検索エンジンの品質判定は「文章」優先
- 短い文章は低品質コンテンツと判定される
ユニーク単語が増える
ユニーク単語とは、コンテンツ内に出現する単語の種類のことです。例えば、コンテンツに「SEO」という単語が30語入っていても1単語とカウントします。ユニーク単語がより多く含まれたコンテンツはユーザーにとって有益な単語の種類が豊富であるとGoogleに評価されます。
また、ユニーク単語が増えることで共起語や関連語を含めやすくなるという二次的効果があります。
- 共起語:メインキーワードから連想される語
- 関連語:キーワード検索の際に検索エンジンが予測変換する語
検索上位に挙がるコンテンツには、ユニーク単語、そして共起語や関連語が各所に含まれています。
SEO対策では共起語や関連語が多数使われていると検索順位が上がりやすい傾向があります。
文字数の多いことはユニーク単語だけでなく、共起語や関連語の増加にまで発展し、さらには検索順位を上げる効果があるのです。また、ユニーク単語と共起語、関連語が多くなると複合キーワード(2~3語の組み合わせで検索する単語)が増加するので、ロングテールSEO対策にもつながります。
検索エンジンの品質判定は「文章」優先
検索エンジンはコンテンツの品位を「テキスト情報」中心で判定する仕組みです。検索エンジンにはクローラーと呼ばれるコンテンツ内部を解読させるロボットが組み込まれており、ロボットの精度は日々上がってきています。しかし、まだテキスト情報以外の画像や動画の内容を完璧に判定できるまでには至っていません。
よって、検索エンジンがコンテンツを判別する材料はテキスト情報に頼っているのが現状です。このような背景があるため、コンテンツ作成においてテキストを主体とした情報の重要度は高まります。とはいえ、デザインや動画はユーザーが情報を読み取る助けにはなるので、積極的に取り入れるべきです。
短い文章は低品質コンテンツと判定される
文字数の少ないコンテンツは低評価を受けやすい傾向にあります。文字数の少ないコンテンツを「低品質」と定義した背景には、Googleアルゴリズムのアップデート「パンダアップデート(2012年実施)」があります。「低品質」なコンテンツを検索上位に表示させないことで検索結果を健全なものへ改善することを目指しました。
また、Googleの「良質なサイトを作るためのアドバイス」というコンテンツ作成のガイドラインの中で、「記事が短い、内容が薄い、または役立つ具体的な内容がない、といったものではないか?」という問いかけがあります。
辞書的な意味を求めるコンテンツは文字数が少なくなることもあるでしょう。しかし、具体的なノウハウを求めるコンテンツの場合は文字数を必要とするのは自明のことです。Googleのアドバイスを丹念に追いかけながらコンテンツ作成することが重要です。
【「低品質」と「良質」コンテンツの比較】
| 低品質なコンテンツ | 良質なコンテンツ |
|---|---|
|
|
低評価を受けないためのコンテンツの作成方法
低評価を受けないためのコンテンツの作成方法は以下の通りです。
- ①キーワードに関する専門知識を得る
- ②網羅性の高い情報をもとにコンテンツ作成する
①キーワードに関する専門知識を得る
最初にキーワードの専門知識について勉強して知識を蓄えます。ユーザーの検索意図を徹底的に理解し、過不足のない情報を提供するには、キーワードに対する専門知識が必要です。また、Googleも公式に専門知識の必要性を説いています。
引用
あなたはこの記事に書かれている情報を信頼するか?
この記事は専門家またはトピックについて熟知している人物が書いたものか? それとも素人によるものか?
良質なサイトを作るためのアドバイス|ウェブマスター向け公式ブログ(Google)
引用
サイト内のコンテンツは、そのトピックの専門家が作成または編集するようにしましょう。たとえば、専門知識や豊富な経験を持つ情報発信者が書いた記事であれば、ユーザーは記事の専門性を理解できます。
専門性と権威性を明確にする|検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド(Google)
Googleにとってユーザーファーストは社是です。それだけにユーザーが必要とするコンテンツ以外は評価しない方針です。
よって、コンテンツ作成者は専門知識についての情報収集は必須です。専門知識が深まれば競合サイトにはない情報をコンテンツに反映することができます。これが「オリジナリティ」となり、Googleからの高評価につながるので、コンテンツ作成者にとってもメリットがあるのです。
②網羅性の高い情報をもとにコンテンツ作成する
網羅性の高い情報を含んだコンテンツの作成の流れは以下の通りです。
- 検索上位サイトの分析する
- アウトラインを決める
- コンテンツの中身をライティングする
1.上位表示されたサイトの分析する
Googleにとってコンテンツとは「検索ユーザーに対する有益な情報」を指します。そのため、どのような情報をコンテンツに落とし込むかどうかを決めなければいけません。
参考にするものは検索結果に出てくる上位サイトです。上位サイトにあるコンテンツはすでにGoogleに「最良の回答」と評価されていることになります。よって、上位サイトを分析することは、最短で優良なコンテンツを作成するヒントになります。
上位1位~10位までのサイト分析は必ず行いましょう。分析のポイントはコンテンツの内容の他、どのようなユーザーが閲覧しているのか、コンテンツのオリジナリティは何か、文字数はどのくらいかなどを意識しながら行いましょう。
なお、文字数を調べるのは、情報の密度、網羅性を確認するために行うことです。「1位のサイトが5000字だから自分も5000字以上書けばよい」などと安直に考えないようにしましょう。
2.アウトラインを決める
コンテンツ全体のアウトラインを作りこんでおくとその後のライティングがスムーズに進みます。アウトラインの作成では、まず収集した情報のもとに見出しを作成します。
見出しには検索キーワードや共起語、関連語を考慮して入れるとよいです。検索キーワードや共起語、関連語が入るとテーマに関連する情報を盛り込むことができます。
また、テーマに一貫した統一感を出すことができます。さらに上位表示コンテンツの傾向だけでなく、独自の内容も盛り込むことでオリジナリティを出せるようにしましょう。
さらにタイトルについても考えておきましょう。タイトルはユーザーが最初に目にする場所であり、瞬時に読むかどうかを判断する指標です。
3.コンテンツの中身をライティングする
アウトラインをもとにコンテンツの中身をライティングしていきます。ライティングの際は以下の点を意識しながら行いましょう。
- ユーザーニーズが満たしているか、随時チェックしながらライティングする
- ライティング途中で必要だと思う情報があれば追加・検討する
- ユーザーは様々な疑問をもつため、逆説や補足事項で情報に広がりを持たせながらライティングする(=情報を網羅させる)
ライティングの段階になると、書くべき内容がおおむね見えてきているでしょう。しかしながら、ライティングの途中でユーザーニーズと乖離していたり、情報の網羅されていないと感じたら、一旦手を止めて上位サイトの分析やアウトライン作成時に残したメモなどを見返すようにしましょう。不安を感じながら書き進めても「良質なコンテンツ」にはなりません。
なお、ライティング途中や最後のチェックリストとして以下の参考サイトを活用することをおすすめします。Googleが公式にリリースするコンテンツ作成のガイドラインです。Googleの文書なので信頼性の高い資料と言えます。
コンテンツ作成の注意点
コンテンツ作成の注意点は以下の通りです。
- コンテンツ全体の統一感
- ユーザーにとって無益な情報
- コピーコンテンツ
- 可読性
- 内部・外部施策
文字数が重要なのではなく、コンテンツの質にフォーカスすることが大切です。質を追求する上でこちらで紹介するポイントは押さえておきましょう、
コンテンツのテーマを統一
コンテンツにテーマの統一感を持たせるようにしましょう。テーマが混在すると検索ユーザーにとって適切なアンサーにならないからです。
例えば、アメリカ留学にかかる費用について調べる場合、「アメリカ留学 費用」というキーワードで検索したとします。アンサーには費用に関する情報でなければいけません。
しかし、費用の他にアメリカ留学におすすめの大学を紹介する内容も書かれていたら、ユーザーは「自分が知りたいのは「費用」のことで、「おすすめの大学」は聞いてない。もっと「費用」について詳しく知りたいのに……」と不満に感じるはずです。
ユーザーが不満を抱けば、ページを即閉じてしまいかねません。そうなると検索エンジンからの評価を得ることができず、検索順位が低くなってしまうでしょう。
したがって、テーマは1ページ=1テーマが望ましいです。テーマが複数入ったコンテンツはユーザーだけでなく検索エンジンにも良いことではないからです。
ユーザーにとって無益な情報
検索順位を上げるためには、ユーザーニーズを満たした網羅性のあるコンテンツが重要です。
しかし、網羅性を意識してユーザーが求めていない情報まで入れてしまったり、文字数稼ぎのために似たような情報を詰め込んで冗長的な文章になってしまうとSEO対策では不利になります。
コンテンツ作成では、ユーザーが求めているであろう情報を過不足なくまとめることが求められます。
もし、書くべきことが見つからない場合は、キーワードに対する知識が不足しているのかもしれません。改めて、専門知識を蓄えることに尽力しましょう。
Googleは「専門知識や豊富な経験を持つ情報発信者が書いた記事であれば、ユーザーは記事の専門性を理解できる」と言及しています。ぜひ専門家になるつもりで知識の習得に努めてみてください。
コピーコンテンツ
他者のコンテンツを無断で使用することは絶対にやってはいけないことです。Googleは「重複コンテンツ」と見なします。
場合によっては、検索エンジンからのペナルティだけでなく、著作権の侵害として法的措置を取られてしまうこともあります。危険性が高い行為なので、厳重に注意するべきです。もし、他者の文章を引用したい場合は、引用元を記載しましょう。
コピー&ペーストしたつもりはなくても、「類似しているのでは?」と不安になる時もあるかもしれません。そのような時は、コピー&ペーストしているかどうか調べられるツールで調べてみるとよいでしょう。判定結果に問題がなければ不安が取り除くことがでます。
可読性
可読性とはユーザーがコンテンツを読んだ時に感じる「読みやすさ」や「わかりやすさ」です。可読性の低いとユーザーはコンテンツに親しみを感じられずに離脱することもあります。可読性を低くする原因には、文字を無駄に増やすこと、誤字脱字、行間が狭くて読みにくいなどがあります。
可読性を低くする行為は、意識的に直していくほかにありませんが、決して難しいことではありません。何度も読み返すことで訂正箇所が見えてきます。また、可読性を上げるために、任意の箇所に飛べる目次機能やコンテンツにメリハリをつけられる画像を活用するのもよい方法です。
SEOの内部対策・外部対策
良質なコンテンツに仕上げるには検索エンジンに対する対策もしておかなければいけません。そこで内部対策と外部対策が必要になってきます。
内部対策とは、Webサイト内のテキストや画像、HTMLタグなど自身で行うコンテンツ内部の改善施策のことです。
コンテンツの内容を適切に検索エンジンに伝えることができる手段です。外部対策とは、外部サイトからの質の高い被リンクを獲得する施策です。被リンクを獲得できるとサイトの評価を上げる効果があります。
サイト内部への対策とサイト外部への対策、どちらも重要な施策が、優先的に行うのは内部対策です。サイト内部を整え良質なコンテンツを発信できると検索順位が上がり、被リンク獲得につながります。
内部対策・外部対策は検索エンジン対策なので、検索上位に表示されるためには必ず行うべき施策です。
しかしながら、もっと大切なことは、コンテンツ対策です。つまりコンテンツの中身を充実させることです。ユーザーニーズを満たしたコンテンツに内部対策や外部対策を施すことでSEO対策は完成されるのです。
したがって、内部対策・外部対策を成功されるには、まずコンテンツ対策が必要であることを忘れてはいけません。
まとめ
コンテンツのテーマから逸れないように注意しながら網羅性のあるコンテンツを作ることで、文字数が増える傾向にあります。
しかし、文字数そのものに重要性はありません。ユーザーの検索意図やE-A-Tを意識したコンテンツを作成することが最も重要なことです。
文字数を気にすることなく、ユーザーファーストのコンテンツを作成することに専念すれば、Googleには適切に評価されます。
- SEO対策でビジネスを加速させる「SEO Dash! byGMO」
-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?
- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・
- コンサルに頼んでもなかなか改善しない
- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる
大事なのは自社にあったビジネス設計です。 御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

 ツイート
ツイート シェア
シェア